定期予防接種
ヒブワクチン
対象者
生後2月から生後60月に至るまでの間にある者
標準的な接種期間
生後2月から生後7月に達するまでの期間
接種回数
初回:3回、追加:2回
※受け始めの月齢によって受ける回数が変わります。
小児用肺炎球菌
対象者
生後2月から生後60月に至るまでの間にある者
標準的な接種期間
生後2月から生後7月に達するまでの期間
接種回数
初回:3回、追加:1回
※受け始めの月齢によって受ける回数が変わります。
BCGワクチン
対象者
1歳に至るまでの間にある者
標準的な接種期間
生後5ヶ月過ぎから8ヶ月に達するまでの期間
接種回数
1回
不活化ポリオワクチン(平成24年9月から)
- 生後3ヶ月過ぎから90ヶ月に至るまで
- 1期初回 20日から56日間隔で3回接種
- 追加 初回3回終了してから1年後に1回接種
三種混合
- 3ヶ月過ぎから90ヶ月に至るまで
- 1期初回 20日から56日間隔で3回接種
- 追加 初回3回終了してから1年後に1回接種
四種混合(DPT-IPV)・二種混合(DT)
〈第1期〉
対象者
生後3月から生後90月に至るまでの間にある者
標準的な接種期間
生後3月に達したときから生後12月に達するまでの期間
接種回数
第1期初回:3回、第1期追加:1回
〈第2期〉
対象者
11歳以上13歳未満の者
標準的な接種期間
11歳に達した時から12歳に達するまでの期間
接種回数
1回
麻しん、風しん混合ワクチン(MR)
〈第1期〉
対象者
生後12月から生後24月に至るまでの間にある者
接種回数
1回
〈第2期〉
対象者
5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前から当該式の達する日の前日までの間にある者
接種回数
1回
水痘(水ぼうそう)
対象者
生後12月から生後36月に至るまでの間にある者
標準的な接種期間
1回目:生後12月から生後15月に達するまで
2回目:1回目の注射終了後6月から12月までの間隔をおく。
接種回数
2回
日本脳炎ワクチン
〈第1期〉
対象者
生後6月から生後90月に至るまでの間にある者
標準的な接種期間
第1期初回:3歳に達した時から4歳に達するまでの期間
第1期追加:4歳に達した時から5歳に達するまでの期間
接種回数
第1期初回:2回、第1期追加:1回
〈第2期〉
対象者
9歳以上13歳未満の者
標準的な接種期間
9歳に達した時から10歳に達するまでの期間
接種回数
1回
〈その他〉
平成7(1995)年4月2日生まれから平成19(2007)年4月1日までの間に生まれ、積極的勧奨の差し控えにより、日本脳炎の予防接種を受ける機会を逃したお子さんは、20歳未満の間に予防接種を受けることができます。
ロタウイルスワクチン(令和2年10月1日から)
ロタウイルスワクチンは2種類あり、どちらも生ワクチン(弱毒化したウイルス)で、飲むワクチンです。医療機関で相談し、どちらかのワクチンを選んでください。なお、途中からワクチンの種類を変更することはできませんので、最初に接種したワクチンを2回目以降も接種します。初回は、出生6週から出生14週6日までに接種します。出生15週0日以降の初回接種はおすすめしません。
〈1価ワクチン〉
対象者
色麻町に住所を有する出生6週から24週にある方
接種回数
2回
接種間隔
27日以上の間隔をあけて接種
〈5価ワクチン〉
対象者
色麻町に住所を有する出生6週から32週にある方
接種回数
3回
接種間隔
27日以上の間隔をあけて接種
予防接種を受けられない方
- 明らかに発熱(37.5℃以上)している方
- 重い急性疾患にかかっている方
- 過去に同じワクチンで強いアレルギー反応が出た方
- 予防接種を受けようとする病気にかかったことがあるお子さん、又は現在かかっているお子さん
なお、上記に当てはまらなくても医師が接種不適当と判断した時は、予防接種を受けることができません。
予防接種を受ける際に注意を有する方
以下に該当するお子さんがいると思われる保護者は、かかりつけ医がいる場合には必ず前もってお子さんを診てもらい、予防接種を受けて良いかどうか判断してもらいましょう。受ける場合には、その医師のところで接種を受けるか、あるいは診断書または意見書をもらってから予防接種を受けるようにしましょう。
- 心臓病、腎臓病、肝臓病、血液の病気や発育障害などで治療を受けているお子さん
- 予防接種で、接種後2日以内に発熱のみられたお子さん及び発しん、じんましんなどアレルギーと思われる異常がみられたお子さん
- 過去にけいれん(ひきつけ)を起こしたことがあるお子さん
けいれん(ひきつけ)の起こった年齢、そのとき熱があったか、その後起こっているか、受けるワクチンの種類などで条件が異なります。必ずかかりつけ医とよく相談しましょう。 - 過去に免疫不全の診断がなされているお子さん及び近親者に先天性免疫不全症の者がいるお子さん
- ワクチンにはその製造過程における培養に使う卵の成分、抗生物質、安定剤などが入っているものがあるので、これらにアレルギーがあるといわれたことのあるお子さん
予防接種を受けた後の一般的な注意事項
- 予防接種を受けた後30分間は、医療機関でお子さんの様子を確認するか、医師とすぐに連絡がとれるようにしておきましょう。
- 接種後、生ワクチンでは4週間、不活化ワクチンでは1週間は副反応の出現に注意しましょう。
- 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位を強くこすることはやめましょう。
- 当日は、激しい運動は避けましょう。
- 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。
予防接種に保護者が同伴できない場合の委任状について
予防接種の実施については、予防接種の効果や副反応及び予防接種健康被害救済制度について理解し、接種後の体調の異常に気づき適切な対処をするため、保護者が同伴するのが原則ですが、保護者がやむを得ない理由により同伴できない場合は、接種を受けるお子さんの健康状態を普段からよく知っており、予診票の内容をよく理解している親族(祖父母等)などが同伴し、予防接種を受けることも可能です。ただし、その場合、保護者の委任状が必要となりますので、下記URLよりダウンロードし、接種当日に医療機関へ提出していただきますようお願いいたします。
予防接種委任状(PDFファイル:89.6KB)
予防接種による健康被害救済制度
定期の予防接種により引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく給付を受けることができます。給付申請の必要が生じた場合には、色麻町保健福祉課へご相談ください。
色麻町保健福祉課保健係0229-66-1700
この記事に関するお問い合わせ先
色麻町 保健福祉課
〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四𥧄字杉成27番地2
電話番号:0229-66-1700
問い合わせフォームはこちら





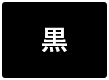

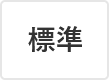
公開日:2021年07月14日
更新日:2022年04月18日