新型コロナワクチン接種について
令和5年度のワクチン接種の概要
令和5年3月8日付けで、新型コロナワクチンの特例臨時接種期間を令和6年3月31日まで延長することが決定されました。
| 時期 | 接種対象者の条件 |
|
【令和5年春開始接種】 令和5年5月8日から令和5年9月19日まで |
初回接種(1~2回目)を終えており、次のいずれかに該当していること ・65歳以上 ・12~64歳で基礎疾患等を有している ・医療または介護関係に従事している |
|
【令和5年秋開始接種】 令和5年9月20日から令和6年3月31日まで(予定) |
初回接種(1~2回目)を終了していること |
令和5年秋開始接種(令和5年9月20日以降)
令和5年秋開始接種では、国内外のウイルスの流行状況や感染対策状況を踏まえて、オミクロンXBB.1系統の株に対応したワクチンを使用します。初回接種(1~2回目)を終えた方が対象で、接種回数は1回です。接種期間は令和6年3月31日までとなっております。重症化リスクの高い高齢者等にはXBB.1系統の株対応ワクチンの接種をお勧めしますが、ワクチンを受ける際には感染症予防の効果と副反応のリスク双方について正しい知識を持った上で、ご本人の意思に基づいて接種を判断いただきますようお願いいたします。
初回接種をご希望の方
個別に対応いたします。初回(1~2回目)をご希望の方は下記までご連絡ください。
色麻町コロナワクチン接種予約窓口:0570-022-292
令和5年9月20日以降のオミクロン株(XBB.1.5)対応ワクチン接種について
集団接種
予約制で行います。使用ワクチンは1価ワクチン(XBB対応)のうちファイザー社製またはモデルナ社製を使用します。
|
接種場所 |
接種日 |
接種日の受付時間 |
|
色麻町保健福祉センター |
10月1日(日曜日) |
午前:8時45分~11時30分 午後:13時00分~15時00分(予定)
|
|
10月14日(土曜日) |
||
|
10月15日(日曜日) |
||
|
10月28日(土曜日) |
個別接種(10月から12月までの間、加美郡内医療機関において行います)
|
接種場所 |
受付時間 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
備考 |
|
中新田民主医院 |
日によって異なる |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
|
⚫ |
⚫ |
※左記⚫の曜日でも実施しない日があります。詳細は予約受付の際にご確認ください。 |
|
佐々木胃腸科 |
15:00/16:00 |
⚫ |
⚫ |
|
⚫ |
⚫ |
|
※左記⚫の曜日でも実施しない日があります。詳細は予約受付の際にご確認ください。 |
|
鈴木内科医院 |
月 14:00 水・土 12:00 |
⚫ |
|
⚫ |
|
|
⚫ |
※祝日除く。 |
|
伊藤医院 |
14:00 |
|
⚫ |
|
|
|
|
|
|
大山医院 |
10:30/16:00 |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
|
⚫ |
|
※祝日除く。 |
|
ありまファミリークリニック |
15:00/16:00 |
⚫ |
|
|
|
⚫ |
|
※祝日除く。 |
|
おのだクリニック |
14:15~15:30 |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
|
※左記⚫の曜日でも実施しない日があります。詳細は予約受付の際にご確認ください。 |
|
鈴木診療所 |
12:30/12:45 |
|
|
⚫ |
|
|
⚫ |
|
|
公立加美病院 |
15:00~15:45 |
11/29(水曜日)、12/5(火曜日)、12/13(水曜日)、12/19(火曜日)、12/27(水曜日) |
||||||
※加美郡外の医療機関で接種を希望される方は医療機関へご相談ください。
※追加接種は、前回の接種から3か月以上経過していることを確認し、予約を行ってください。
接種券の発送について
◆12歳以上の方には順次発送いたします。
◆5歳から11歳の追加接種対象となる方には、準備が整い次第順次発送いたします。
◆他自治体から色麻町へ転入された方で接種を希望される場合は、接種券の発行申請が必要です。ご連絡いただくか、電子申請をご利用ください。
◆お手元の接種券を使用できる場合もございます。紛失された方はご連絡ください。
なお、電子申請も受け付けておりますので、接種券を紛失された方はご利用ください。
https://www.shinsei.elg-front.jp/miyagi2/uketsuke/form.do?id=1681274837483
予約について
令和5年9月11日(月曜日)~9月29日(金曜日)
予約方法
1.インターネット予約(24時間受付)
〈色麻町ワクチン接種予約受付サイトURL〉
https://taskcore.tkc.jp/cu/044440/r1/residents/procedures/procedure/

2.電話予約(平日9:00~17:00)
色麻町新型コロナワクチン予約専用 0570-022-292
お願い
- 接種当日は自宅で体温を測定し、明らかな発熱がある場合や体調が悪い場合には、接種を予約した医療機関までご連絡ください。
- 体調不良や都合がつかず、変更・キャンセルをする場合には必ず医療機関までご連絡ください。
- 予約状況により予約日の変更をお願いする場合があります。
- 接種曜日や受付時間等の変更がある場合は、ホームページに掲載いたします。
- 一人につき一つの医療機関に予約をお願いいたします。(重複予約のないようにお願いいたします)
- 新型コロナワクチンと他のワクチンとの接種間隔は、13日以上あけてください。ただしインフルエンザワクチンは同時接種が可能となりました。(令和4年7月22日以降)
問い合わせ先:0570-022-344(色麻町ワクチン接種相談ダイヤル)
宮城県新型コロナウイルスワクチン副反応相談センター
ワクチン接種後の健康相談を下記のコールセンターで受け付けています。
宮城県新型コロナウイルスワクチン副反応相談センター
電話:050-3615-6941(8時45分~17:15)
Eメール:m-side-reaction@medi-staffsup.com
ファックス:022-200-2932
接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度
一般的にワクチン接種後には、ワクチンが免疫をつけるための反応を起こすため、接種部位の痛み、発熱、頭痛などの「副反応」が生じる可能性があります。治療を要したり、障害が残るほどの副反応は、極めて稀ではあるものの、ゼロではありません。予防接種による健康被害が起きた場合には、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。
申請は、下記の必要書類を作成・準備のうえ、保健福祉課へ御提出いただきます。
なお、申請から給付が決定するまでは、数ヶ月から1年程度の時間を要する場合もあります。(不認定となり給付対象外となる場合もあります。)
詳細は、下記「予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)」をご覧ください。
給付の流れ
給付に必要な書類を受理した後、色麻町予防接種健康被害調査委員会において医学的な知見から当該事例について調査し、その結果を、県を通じて国へ進達します。
国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、県を通じて本町に通知をします。
その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。
給付の種類
| 給付の種類 | 請求者等 | 給付額 |
| 医療費 | 予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者 | 健康保険等による給付の額を除いた自己負担分 |
| 医療手当 | 同上 | 通院3日未満35,800円/月 通院3日以上37,800円/月 入院8日未満35,800円/月 入院8日以上37,800円/月 同一月入通院37,800円/月 |
| 障害児養育年金 | 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者 | 1級1,617,600円/年 2級1,293,600円/年 |
| 障害年金 | 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の者 | 1級5,175,600円/年 2級4,138,800円/年 3級3,104,400円/年 |
| 死亡一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族 | 死亡一時金45,300,000円 |
| 葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者 | 212,000円 |
| 介護加算 | 施設入所または入院をしておらず、養育されている場合、障害児養育年金または障害年金を加算するもの | 1級846,200円/年 2級564,200円/年 |
※給付額は、令和5年6月現在の内容です。
※事例により、表の給付額と異なる場合があります。
申請に必要な書類
| 医療費 医療手当 |
障害児 養育年金 |
障害年金 | 死亡一時金 遺族年金 遺族一時金 |
葬祭料 | |
| 請求書 | ⚫※2 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| 受診証明書 | ⚫※3 | ||||
| 領収書等 | ⚫※4 | ||||
| 診断書 | ⚫※6 | ⚫※6 | |||
| 死亡診断書等 | ⚫※10 | ⚫※10 | |||
| 埋葬許可証等 | ⚫※11 | ||||
| 接種済証又は母子手帳 | ⚫※1 | ⚫※1 | ⚫※1 | ⚫※1 | ⚫※1 |
| 診療録等 | ⚫※5 | ⚫※7 | ⚫※7 | ⚫※12 | ⚫※12 |
| 住民票等 | ⚫※8 | ⚫※14 | |||
| 戸籍謄本等 | ⚫※9 | ⚫※13 | ⚫※13 |
※請求に必要な書類の様式は、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
※同時請求の場合、重複する書類は省略可能
※請求書、受診証明書、診断書以外は全て写しで可
| 共通 | ※1.受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証又は母子手帳の写し |
| 医療費 医療手当 |
※2.医療費・医療手当請求書 通院・入院日数の欄が足りない場合は、任意で別紙作成することも可 ※3.医療機関又は薬局等で作成された受診証明書 ※4.医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等の写し ※5.疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し ただし、新型コロナワクチンによる、アナフィラキシー等の即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したもの(ただし、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は診療録等の写しが必要です。)に係る請求に限り、医療機関で様式5-1-1の記載を受けて提出すれば、診療録等は不要になります。 |
| 障害児 養育年金 障害年金 |
※6.障害の状態に関する医師の診断書 障害児養育年金の給付を受けている方が障害年金の申請を行う場合は18歳の誕生日以降に作成された診断書であること ※7.障害児・者が予防接種法施行令別表第1、第2に定める障害の状態に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し ※8.障害児の属する世帯全員の住民票の写し ※9.障害児を養育することを明らかにすることができる戸籍の謄本、抄本又は保険証の写し |
| 死亡一時金 遺族一時金 遺族年金 葬祭料 |
※10.死亡した者に係る死亡を証する死亡診断書又は死体検案書の写し ※11.請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証又は葬儀案内状等の写し ※12.予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し ※13.請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本の写し ※14.(死亡一時金・遺族一時金)請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写し ※14.(遺族年金)請求者が死亡した者の死亡当時その者によって生計を維持していたことを証する住民票等の写し その他 請求者が死亡した者と内縁関係にあった場合は、その事実に関する当事者(内縁関係にあった夫及び妻)双方の父母、その他尊属、媒酌人若しくは、民生委員等の証明書または内縁関係にあったと認められる通信所その他の書面 |
リーフレット「ご存じですか?予防接種ご健康被害救済制度」 (PDFファイル: 560.0KB)
注意
1.「コロナワクチンの予約をとる」などといって町の職員が金銭や個人情報を電話で求めることはありません。不審な電話にご注意ください。
2.ワクチンを受けるにはご本人の同意が必要です。現在、何かの病気で治療中の方や、体調など接種に不安がある方は、かかりつけ医とご相談の上、ワクチンを受けるかどうかお考えください。なお、ワクチン接種は強制ではありません。接種を行う前に「ワクチンの効果」と「副反応のリスク」について理解した上で、自らの意思で接種を受けていただくこととなります。同意がないまま接種が行われることはありません。
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
電話番号
0120-761-770
受付時間
9時00分から21時00分
新型コロナワクチンについて(厚生労働省ホームページ)
ワクチンに関する詳細は、厚生労働省ホームページをご確認ください。
なお、本ホームページの掲載をもって、予防接種法施行令第5条に規定される公告を行ったことといたします。
この記事に関するお問い合わせ先
色麻町 保健福祉課
〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四竃字杉成27番地2
電話番号:0229-66-1700
問い合わせフォームはこちら





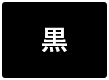

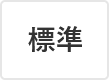
公開日:2023年09月06日
更新日:2023年09月04日